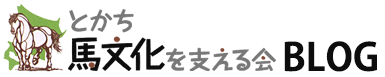掲載順が前後しますが……
帯広競馬場に隣接する商業施設「とかちむら」の要請を受け、同施設前で、当会ポニー・エクレア号でのイベントを開催しました。
イベントは午前と午後の2部制とし、午前は、来場者にエクレアを撫でたり、写真を撮ったり、と、ふれあいを楽しんでいただきました。
午後は、エクレアの気分転換のためもあって、「ポニーの食べないもの当てクイズ」を実施。並べられた草や野菜などの中から、ポニーが「食べないもの」と思う食べ物を各自、選んでもらい、それをエクレアにあげて、食べなければ当たり! 商品として馬シールを贈呈。
ということで、参加してくれた子供たちは、エクレアが嫌いそうな食べ物を探すのですが……。
食べなければ、当たりのシールがもらえますし、食べたらハズレ、ではありますが、エクレアが美味しそうに食べる姿に満足。ということで、たくさんの子供たち、そして、おとなも参加して、エクレアの動向に一喜一憂。ただし、エクレアは偏食お嬢様。他の馬なら喜んで食べるカボチャにもプイッと横を向いてしまうなど、馬らしからぬ食性で参加者を翻弄していました。

とかちむらから提供された美味しそうなレタスを差し出されて……これにも偏食お嬢様は採食拒否